
これまで2回、醸しの半島、知多と題し、知多半島が江戸時代以降、醸造品の質・量・多様性において国内有数の一大醸造地帯に発展してきたようすを酒・ビール・味噌・溜・醤油・みりんについて紹介してきました。今回は、このシリーズの特別編として、これまで紹介してきた当地の醸造業のあゆみと食文化との関係を示す資料を中心にミニ展示を行いました。併せて、伝承料理研究家の奥村彪生先生による「江戸末期〜昭和の食文化」と題した講演と料理研究家の浜内千波先生による豆味噌をつかった「卵そぼろ」ほか3メニューの料理実演により、醸造や食文化についての歴史が気軽に楽しく聞け、家庭で手軽に今晩のおかずにいかしてもらえる内容で開催しました。

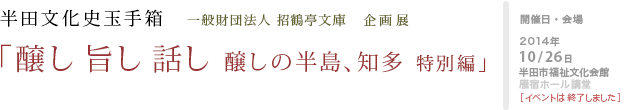
酒は日本人の生活に欠かせないものです。縄文時代にはすでに酒が飲まれていたといわれています。現在の日本酒に近い製法が開発されたのは、15世紀ごろと考えられています。平和が訪れた江戸時代、経済活動が活発になり人々の生活が豊かになるにつれ、酒を飲む場面が一段と増えました。そのため、江戸時代には日本各地で酒造りが行われ、知多半島にも17世紀末には100人以上の酒造家がいました。
18世紀後半、知多半島の酒造業は発展期を迎えました。江戸という大市場へ積極的に進出を始めたのです。それまで伊勢湾周辺から江戸へ行く酒の中心は三河の酒でしたが、それにかわって尾張の酒が江戸へ運ばれるようになりました。尾張藩も酒の江戸市場での販売は貴重な「外貨」獲得のチャンスだったので、酒造業の保護育成をはかりました。19世紀には知多半島に半田・亀崎を中心に1000石を超す大きな酒蔵がいくつも生まれ、最盛期には200蔵以上の酒蔵がありました。
江戸では上方の酒が好んで飲まれました。上方の酒造りの中心は、江戸時代前半は伊丹(兵庫県)・池田(大阪府)、江戸時代後半以降は灘・西宮(兵庫県)でした。上方より江戸に近く海上輸送の便に優れていた伊勢湾周辺は、江戸積みの酒では上方に次ぐ酒造地帯で、江戸に入る酒の10〜15%が伊勢湾周辺で造られた酒でした。伊勢湾周辺の酒は、江戸と上方の中間にあたる地域で造られた酒という意味で「中国酒」とよばれました。
知多半島の酒がシェアを獲得できた理由の一つは、その品質の高さです。雑菌が繁殖しにくい寒い時期に酒の仕込みを行う寒造り、十分発酵させて味わいのある酒を造る段仕込みなど、知多半島の酒造家は上方の進んだ製法を取り入れてきました。明治時代になると、化学技師である宇都宮三郎を招いたり、醸造試験場を設けたりと、灘に負けないように化学に裏打ちされた酒造りに取り組みました。

知多半島や西三河南部は、酒造りだけではなくさまざまな醸造業が展開しているところに特徴があります。江戸時代から現在まで、味噌・溜・醤油やみりん、酢などの醸造品が造られてきました。また、これらの製品が地元での消費だけではなく全国市場をターゲットとして生産されていることも特徴です。
知多半島の味噌造りは、17世紀後半に大野(常滑市)の三河屋(萩原)宗平が始めたと伝えられています。岡崎の八丁味噌も創業は17世紀にさかのぼるといわれています。18世紀には小鈴谷(常滑)の盛田久左衛門も味噌造りを始めました。江戸へ酒などを運んだ船は帰り荷物として関東・東北産の大豆を積んで伊勢湾へ戻ってきました。上方・瀬戸内と関東の間を航行していた船が、瀬戸内産の塩をもたらしました。
明治時代になって急激に味噌・溜の醸造がさかんになったのが、大足地区(武豊町)です。幕末期には数軒しかなかった醸造業者は、明治末期には25軒を超すまでになりました。不況に陥った酒造業からの転業が多かったことに加え、武豊港が開港場になったため大陸産の大豆が入手しやすくなったこと、武豊線が開業して陸上・水上両方の交通網が整備されたことなどが、味噌・溜醸造業が発展した理由です。
さかんな酒造業を背景に造られるようになったのが、みりんと酢です。酒を搾る時に副産物として生み出される酒粕を原料として、みりんや酢が造られました。18世紀半ばに創業した大浜(碧南市)の石川八郎右衛門家は、酒・焼酎を造り、さらに酒粕を原料としたみりん造りを始めました。石川家のみりん造りの技術が広がり、また明治時代以降アルコール度数の高い焼酎と米を使って発酵させる製法が定着して、大浜ではみりん醸造業がさかんになり、全国でも有数のみりん生産地になりました。半田の中埜又左衛門家ももとは酒造家でしたが、酒粕を原料とする酢造りが軌道にのると酒造りと酢造りを分離して、酢造りを本業として現在に至っています。

味噌や醤は、塩とならんで古くからある調味料です。東アジア・東南アジアから伝来した醤がもとと考えられています。飛鳥時代に、醤を原形とした味噌の製法が伝えられて日本の味噌造りが始まりました。古い時代の穀醤はどろっとしたもので、現在のような液状の醤油は、13世紀に伝わった径山寺味噌を造る過程で得られる溜醤油が始まりでした。
しかし、味噌は「手前味噌」の言葉があるとおり自分の家で造るのが一般的でした。醤油も味噌造りの副産物として家で造られました。江戸時代には味噌も醤油もしだいに商品として販売されるようになりましたが、当初醤油は酒よりも高価な調味料でした。それに比べて味噌は安い調味料として料理に多用され、味噌汁が毎日飲まれるようになりました。
塩と味噌を基本的な調味料とした食のあり方が大きく変化したのは18世紀半ば以降です。銚子・野田(千葉県)など江戸近郊で、小麦を使った香りのよい醤油が大量生産され江戸市場を席巻しました。また、調味料の種類も増えました。甘い酒として飲まれていたみりんが調味料として使われるようになり、国産の砂糖も生産量が増加して市場に出回るようになりました。中埜家が粕酢を造り江戸へ販売し始めたのは19世紀初めのことです。
多種類の安い調味料は、だしと組み合わされて和食を発展させました。醤油とみりんで作ったたれを付けた鰻の蒲焼きは、「土用の丑の日には鰻を」という宣伝とあいまって人気を博しました。香ばしい醤油は蕎麦とよく合います。甘み・旨みの強い粕酢は早ずしに使われ、消費量が急速に増大しました。
明治時代になって政府は「衛生」「健康」といった新しい価値観を浸透させようと、牛乳や肉食を奨励しました。しかし、好奇心はあっても従来の食生活がすぐに大きく変わることはありませんでした。それでもしだいに和洋の食習慣が融合した新しい食習慣が生み出されました。明治初年にはあんパンが発明され、19世紀末ごろにはトンカツのような日本で生まれた洋食ができました。

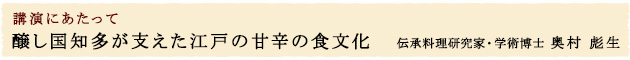
知多の重要な産業は醸造業である。酒や味噌、醤油、味醂、酢などの発酵食品がその代表である。これらは総てウルトラスーパーマンがスターターになっている。そのウルトラスーパーマンは白い体を白のジャケットと白のズボンで身を包み、白いマントを羽織っている。
その正体は、うまみを生み出すカビである。このカビが現在は国菌になっており、名はアスペルギルス・オリゼという。
江戸は元禄以後には百万都市になり、一大消費地となった。知多の醸造品は海運ネットワークで江戸に直接運ばれた。江戸の文人や食通が足繁く通った高級料理亭八百善が出版した『江戸流行料理通』[1835年(天保6年)]の味噌吸物の部に尾張や三河の味噌が出てくる。
吸物は酒肴で、汁も実も椀に上品に盛り、蓋をつけた。汁物は飯のおかずで汁も実もたっぷり入れ、蓋なしである。
百万都市江戸で発達した庶民(約五十万)の食べものは屋台のファストフードである。
鰻が開かれ、味醂、溜醤油のたれを塗ってうまく艶よく焼かれた蒲焼が生まれるのは1700年代終わりごろ。1829年(文政12年)の『遊暦雑記』(江戸叢書)に溜醤油三合、味醂一合、白砂糖弐拾匁目とある。やがてうな重やうな丼が生まれる。
そば切のつけ汁(辛汁)にも味醂が加わる。あるそば屋の伝書に極上々土佐節水八升に付五百匁目、極上々味醂弐升、極上々醤油三升となっている。
八百善の料理の味付けにも味醂醤油が用いられており、かまぼこや真薯の味付けにも用いている。
江戸後期には一人鍋が人気で鰹のだしと味醂は欠かせなかった。どぜう鍋やねぎま鍋、鴨鍋などがあった。ぼたん鍋は豆味噌と溜醤油、味醂を合わせて煮た。このたれに鴨肉や鯨肉を漬けて鋤で焼くとすき焼。
ファストフードの屋台の天麩羅屋のつけ汁も醤油と味醂とだしで作った。割り醤油という。握りずしのタネにする穴子やするめいか、鳥貝などは味醂醤油でサッと煮た。鮪の赤身は霜降りをして醤油に味醂と花鰹を加えて煮た土佐醤油に漬け、づけにした。
醤油と味醂で調味のバランスを取ることを両味といった。
大豆のみで造る味噌や溜醤油はご当地で誕生する。なぜ、味噌や溜醤油は大豆だけ用い、長期熟成させるのか。その理由は特産品として紀州や関東、他の産地との差別化を図った。色は濃く、うまみが強い点に重点を置き、優位に立とうとしたのではないか。
味醂や赤酢も三年間熟成させ、味にコク(深味)を出した。味醂や赤酢の原料は酒造りの副産物である酒粕を利用したために比較的安く調達できた。これなら三年熟成させても元は取れる。豆味噌や溜醤油は大豆を安く仕入れる工夫をし、無駄をしない合理的経営手法を取ったと考えられる。そのことが会社に体力をつけ、資本に余裕を生み出した。
江戸後期、蘭学者によって獣肉や牛、豚の肉食は滋養食として推しすすめられていた。幕末には京都の三条大橋のたもとに牛鍋屋が三軒並んでいた。大阪にもあり、ここで一万円札の顔、福沢諭吉が食べていた。京阪には軍鶏鍋もあった。
明治生まれの牛肉料理はなんといっても牛鍋とすき焼。牛鍋には割り下といって醤油、味醂、酒、砂糖を合わせた甘辛たれは欠かせない。豆味噌、溜、味醂、酒で仕立てた牛鍋屋は今も横浜にある。
そしてトンカツ。ところでトンカツってどこの国の言の葉でしょうか。トンは中国語、カツはカットレットでフランス語。
やがて牛丼やカツ丼、親子丼、天丼と米飯が沢山食べられる丼物が登場する。そのルーツは江戸時代のうな丼である。
と作詞作曲したのは古賀政男だが、日本人は古代から嬉しいにつけ、悲しいにつけ、酒を飲んできた。上手に飲めば百薬の長、誤ればわが身を滅す。古代の日本の酒は飯を口に入れて噛み、壺に入れて発酵させた口噛酒であった。糀(クモノスカビ)を用いて発酵させる醸造技術は応神天皇のころ、朝鮮半島から伝わった。日本酒がうまくなるのはアスペルギルス・オリゼが選抜された400年前からである。醸造酒では世界一アルコール度数が高く、そのうえ世界一うまみを多く含んでおり、水のごとく清らかである。
酒は心のうさを晴らすための飲み物ではない。人と人の絆を結ぶための宴には欠かせない。酒に含まれているアルコールが人の心を開き、愉快にさせてくれる。古代の日本人は酒を様々な呼び方をしている。例えば、
キ: 『古事記』に「この御酒を醸みけむ人は、その鼓臼に立て、歌ひつつ、…舞ひつつ…」とある。
クシ:人を酔わして怪しという意味である。『古事記』に「須須許理が醸みし御酒に我酔ひにけり、事無酒、笑酒…」と詠われている。
ササ:酒を人にすすめる時、さぁさぁという。これがなまり、ささとなり、竹葉と書く。『古事記』に「御酒のあやにうた楽し、ささ」とある。
サケ:酒にひたることをさかみづくといい、なまって栄え水、更になまってさけになったという。
古代の貴族達は優雅に酒を楽しみ、友情を高めている。琴の音のなか酒を飲み、漢詩を作っている。
雪見酒。風流なる遊びである。遊び心が文化を向上させる基本である。万葉集に雪、月、梅(花)の日本の風流を詠んだ和歌がある。
雪の上に照れる月夜に梅の花折りて贈らむ愛しき児かも(大伴家持)
また、梅の花弁を浮かべて飲んでいる。
酒杯に梅の花浮かべ思麩どち飲みての後は散りぬともよし(大伴坂上郎女)
春三月になると琴や歌声がとどろくなか、曲水に酒を盛った盃を流し、自分の前に来るまで漢詩や和歌を作る高尚な酒宴があった。
庶民のおんなひとも飯と糀で一夜酒を造り、いとしい彼を待った。「味飯を水に醸みなしわが待ちし代はかつてなし直にしあらねば」と万葉集にある。
日本酒はうまみを持っているから、その味を生かすためには塩気を含んだものが最も合う。その最たるものは塩であり、古代からこれは用いられていた。そして塩辛。古代には鮑腸漬や鮑雲丹交作、鮎うるかや海鼠腸、馴鮓、膾(イノシシ、シカの生肉)、割レ鮮(刺身)、干肉、干物、漬物などが用いられている。ていた。そして塩辛。古代には鮑腸漬や鮑雲丹交作、鮎うるかや海鼠腸、馴鮓、膾(イノシシ、シカの生肉)、割レ鮮(刺身)、干肉、干物、漬物などが用いられている。
中世になると刺身は材料によってソースを変え、蒲焼やかまぼこ、田楽、雑煮などが用いられた。
江戸後期になると料亭料理が発達するが、その料理は主に酒の肴であり、その伝統が現在も続いている。ここは武家や商人、文人が利用した。長屋住まいの独り者の楽しみは振り売りのおでん熱燗。そして居酒屋に出向いて一人鍋や白魚やかきの玉子とじなどでチビリチビリと飲った。長屋住まいの夫婦者では芋たこや鮪のぬた、あさりや芝えびのおから煮、蒸し蛤、なまこの生姜酢などを手作りして用いていた。